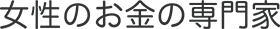「大学に行きたい」子どもの願い、諦めないで!シングルマザーが経験した教育費と奨学金

宮城県在住 女性のお金の専門家の浅野由香です。
「子どもの教育費、どうしよう…」「奨学金って複雑でよくわからない」そんな不安を抱えていませんか?
私もかつて、シングルマザーとして3人の子どもたちを育てる中で、まさに同じ壁にぶつかりました。特に子どもが「大学に行きたい」と言い出した時、正直なところ「どうやって学費を工面しよう…」と頭を抱えました。
でも、諦めずに情報収集し、様々な制度を活用することで、なんとか子どもの願いを叶えることができました。今回は、私の実体験を交えながら、教育費と奨学金のリアルな話、そして「知っておいてほしい注意点」をお伝えします。ぜひ、あなたの教育費の不安を解消するヒントにしてくださいね。
リアルな教育費の壁!私のシングルマザーとしての挑戦
子どもが小さい頃は、パート勤めで何とか生活できていました。非課税世帯の恩恵を受け、児童扶養手当や医療費控除に助けられ、「何とか今月も乗り切れた」とホッと胸をなでおろす日々。でも、通帳とにらめっこしながら「来月のお給料、足りるかな?」と常に不安と隣り合わせでした。
子どもたちの成長とともに、食費も光熱費も、そして習い事や部活動の費用もどんどんかさんでいきました。生活費を捻出するために始めたのは、仕事の掛け持ちです。慣れない複数の仕事を掛け持ちする日々は本当に大変で、心身ともに疲弊していました。
そんな中、子どもたちの不登校を経験し、一度は仕事を辞めるという選択もしました。「何のために働いていたんだろう…」と自分を責める日々もありました。失業手当をもらいながらの生活は、貯蓄に回す余裕などありません。
そんな矢先、長男から「大学に行きたい」という願いが。正直、途方に暮れました。でも、子どもの夢を諦めさせたくない一心で、まとまった貯蓄がなくても大学に行ける方法はないかと、親子で模索を始めたのです。
奨学金活用のリアルと知っておきたい注意点
長男の大学進学を前に、私たち親子がぶつかったのは「まとまった初期費用」という壁でした。幸い、長男の高校の推薦枠で、大学独自の奨学金(入学金と前期授業料を大学が負担してくれるもの)を利用できることになり、本当に助けられました。しかし、奨学金は複雑で、知っておくべき注意点がありました。
注意点1:奨学金には様々な種類があり、申請時期と条件が非常に重要!
長男が利用できた大学独自の奨学金は、高校からの推薦が必要でした。また、大学によっては入学前に申請が必要なもの、入学後に申請できるもの、学力基準や家計基準が異なる給付型・貸与型など、本当に多種多様です。
【私の経験から】 私たちの場合、高校の先生から情報提供があり、早期に動けたことが非常に幸運でした。もし情報が遅れていたら、初期費用の壁を乗り越えられなかったかもしれません。 子どもの進路が決まり始めたら、まずは高校の先生や大学の入試課に相談し、利用できる奨学金の種類と申請時期、そして条件を徹底的に確認することが大切です。特に、入学前に締め切りがある奨学金は多いので注意が必要です。
注意点2:奨学金の併用にはルールがある!「給付型だから安心」は要注意
長男は大学独自の給付型奨学金で入学し、2年目からはJASSOの第一種奨学金(無利子)を併用していました。しかし、3年目から始まった国の「給付型奨学金(高等教育の修学支援新制度)」に切り替えた際、思わぬ落とし穴がありました。
【私の経験から】 「給付型だから安心」と思っていたら、大学独自の奨学金との併用が認められず、大学の奨学金は打ち切られてしまいました。息子は一人暮らしだったので、給付型奨学金だけでは生活が苦しく、高校時代のバイト代を切り崩して何とか凌ぐ日々。私もパートを掛け持ちして、必死に家計を支えました。 複数の奨学金を利用しようと考えている場合は、必ずそれぞれの奨学金の「併用可否の条件」を確認してください。特に、給付型奨学金は生活費の足しにもなりますが、併用ルールをしっかり把握していないと、予定していた支援が受けられなくなる可能性があります。
注意点3:家族構成や収入の変化で奨学金支給区分が変わる可能性がある!
三男が大学に進学する際、長男が就職し、次男もいずれ就職するかもしれないという状況でした。この時、給付型奨学金と授業料減免の「区分」が非常に重要になってきました。
【私の経験から】 次男が扶養から外れると、私の正社員としての収入では、給付型奨学金の対象から外れてしまう可能性が出てきたのです。「せっかく頑張って正社員になったのに…」と焦りました。 給付型奨学金は、世帯収入や扶養している家族の人数によって、支援区分(第一区分、第二区分など)が変動します。そして、扶養人数が減ったり、世帯収入が増えたりすると、支援区分が変わり、支給額が減ったり、最悪の場合は対象外になったりするリスクがあります。 子どもの進学中に家族の就職や退職、結婚など、家計に影響を与える変化があった場合は、すぐに奨学金窓口に相談し、支給条件に変更がないか確認しましょう。
不安が安心に変わった!iDeCoで賢く教育費と老後資金を準備する
奨学金の支給区分が変動するかもしれないという不安に直面し、私は「何とかしなければ」と一念発起してお金の勉強を始めました。そこで出会ったのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)です。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、iDeCoは自分で選んだ金融商品に投資し、掛金を運用していく私的年金制度です。実はこのiDeCo、掛金が全額所得控除の対象になるため、課税所得が減り、結果的に住民税や所得税が安くなります。この税制優遇が、給付型奨学金の対象基準となる世帯年収の計算に大きく影響する可能性があるのです。
【私の経験から】 私は、まさにこのiDeCoを満額活用することで、危うく対象外になりそうだった三男の給付型奨学金(第一区分)を維持することができました。iDeCoをかける前と後でシミュレーションしてみると、その差は約200万円もの支援額!本当に恐ろしいほどの差が出ました。
結果的に次男は扶養から外れませんでしたが、いつ何があるか分からないのが人生です。iDeCoを始めたことで、「いつ扶養から抜けても大丈夫」という安心感を得ることができました。
さらに嬉しいことに、iDeCoは老後資金の形成にも役立ちます。私はまだ2年ほどですが、月23,000円の掛金で、すでに53万円の掛金に対し13万円の利益が出て、合計66万円の資産を築くことができています。
iDeCoは、子どもの教育費支援の対策になるだけでなく、自分の老後資金を賢く準備できる強力な味方です。

お金の知識で子どもの未来と自分の老後を守る
私の経験から強くお伝えしたいのは、お金の勉強は、子どもの未来を切り開くと同時に、自分自身の老後の安心も守る、とても大切なことだということです。
奨学金制度は複雑に感じられますが、適切な情報を得て、賢く活用すれば、子どもの「大学に行きたい」という願いを叶える強力なツールになります。そして、iDeCoのような税制優遇のある制度を味方につければ、教育費の不安を軽減しながら、老後への備えも同時に進めることができます。
もし今、あなたが教育費や奨学金、老後資金について不安を感じているなら、ぜひ一歩踏み出して、情報収集や制度の活用を検討してみてください。このブログが、少しでも皆さんの希望の光になれたら嬉しいです。
※制度の内容は変更される場合がありますので、最新の情報は各機関のウェブサイトをご確認ください。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金トップページ
- 奨学金制度全般(給付型、貸与型、海外留学など)に関する詳細な情報が掲載されています。
- URL: https://www.jasso.go.jp/shogakukin/
文部科学省の「学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度」
- 特に「高等教育の修学支援新制度」(授業料等減免と給付型奨学金)に特化した情報が豊富です。
- URL: https://www.mext.go.jp/kyufu/
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!