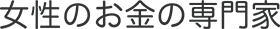幼少期から始める子どもの金銭教育の大切さ
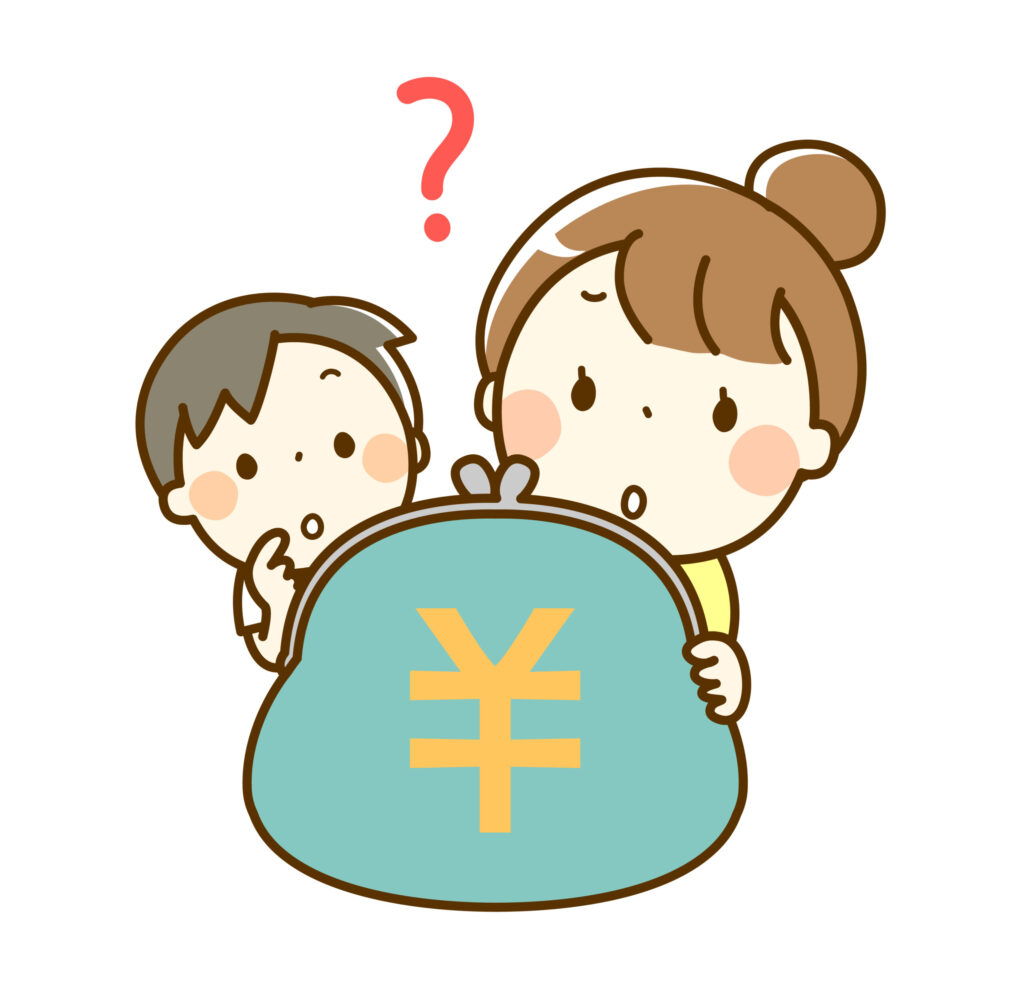
こんにちは! 子育てママのお金の専門家
マイライフエフピー®認定ライター・認定講師の池田ひろみです。
突然ですが、お子さんの金銭感覚について心配なられたことはないですか?
先日ママ友と話題なった子どもの金銭感覚についてご紹介します。
そのママは私立大学を卒業され、学生時代は周囲も含めて経済的に恵まれた家庭の子ばかりだったとのこと。
ママ曰く、「何でも買ってもらえるのが当たり前」で、欲しい洋服、バッグ、旅行、ブランド品..など、欲しいと思えばすぐ手に入る環境だったそうです。
でも社会人になり、その「当たり前」は実は特別なことだったと気づいたそうです。
「ありがたかったと思うけど、お金のありがたみや使い方を知らずに大人になってしまったことは、正直反省してる」
そして今子育てをしている中で、「自分の子どもには、欲しいモノが簡単に何でも手に入るのが当たり前と思って欲しくない」と感じているとのこと。
しかし、おじいちゃん・おばあちゃん(祖父母)が、孫のかわいさに何でも買い与えたり、簡単にお小遣いをくれるため悩んでいると。

幼少期から始める「金銭教育」の大切さ
実はこのようなお悩みは多くのご家庭で聞かれます。実際、我が家でも同じような出来事がありました。
子どもに金銭感覚を身につけさせたい親心と、孫に喜んでほしい祖父母の気持ち、どちらも愛情からくるものですがバランスがとても大切です。
日本では「お金の話を家庭でするのはちょっと、、、」という風潮がいまだにありますが、家庭で話さないことでお金に対する無知や浪費、家計のトラブルを招いてしまうこともあります。
幼少期から金銭教育を始めるメリットは、以下の3つです。
1.お金の「見え方」が変わる
値段の違いや、モノの価値を比較する力がつき「お金は価値と交換する道具」という考え方が身に付きます。
2.自己管理能力が育つ
予算の中でやりくりする力は、大人になってからも必須です。
3.【欲しい】と【必要】を判断できるようになる
衝動買いを防ぎ、将来の資産形成にもつながります。
中学生になると、親の目が行き届かなくなります。交友関係や行動範囲も広がるため、使う金額も大きくなりがちです。
金銭トラブルに巻き込まれないためにも、早めに金銭教育でお金の感覚を身に着けさせておきましょう。

ご家庭でできる金銭教育のステップ
1.お小遣い制を導入する
毎月決まった金額を渡す「月額制」、お手伝いをしたら渡す「成果報酬型」など、ご家庭にあったスタイルでやってみましょう。
2.目標を立ててお金を貯める体験をする
「将来欲しいモノのために、今少し我慢する」という経験を通して、お金は計画的に貯めて使うことを学びます。
3.お買物に一緒にいく
一緒にお買物に行き「A店では○○円だったけど、このお店では△△円だね。」など、同じ商品でもお店によって価格が違うことや似たような商品でいくらの金額差があるのかを一緒に考え、どちらが自分にとって良いのか選択する力が養えます。
4.親の金銭感覚を見せる
「旅行のために毎月貯金をしている」「欲しいモノリストを作って優先順位をつけて購入している」など日頃の親のお金の使い方を話すようにしましょう。もちろん、失敗した経験を共有するこも大切です。
5.一緒に振り返る
「このお金の使い方は価値があったのか」を振り返る習慣をつけましょう。振りかえることで成功体験・失敗体験を次回に活かし、自分にとって価値ある使い方が分かるようになっていきます。
最後に
金銭感覚は一朝一夕で身に付くものではありません。
大人になってから突然「計画的に使いましょう」と言われても、身に付いてない習慣は簡単には変えられません。
だからこそ、小さいうちから「自分で考え、判断する経験」を積んでいくことが重要です。
家庭の経済状況に関わらず、「欲しいモノがすぐ手に入る」ことが当たり前になってしまうと、お金の価値や労働の意味を実感する機会がなくなってしまいます。
逆に「待つ・計画する・選ぶ」経験を積んだ子どもは、大人になってからお金の管理にも強くなります。
親子で一緒に学ぶつもりで、楽しみながら金銭感覚を育てていけると良いですね♪
具体的なお小遣いのルール作りや教育資金についてはお気軽にご相談ください(*^^*)

FPオフィスClear 池田ひろみ