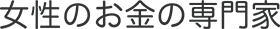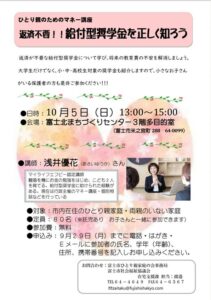【体験談】FPの私が公的機関に家計相談に行って気づいたこと

こんにちは。
名古屋市在住のマイライフエフピー®認定ライター・女性のお金の専門家 山根純子です。
現在、私はFPとして、お金に関する情報を発信し、相談を受ける立場にいます。
しかし、時には自分自身の家計について悩むこともあります。
今回は、夫の退職金の受け取り方について迷い、税務署に相談に行ったときの経験をお伝えします。
退職金の受け取り方が大切な理由
退職金は「一時金」と「年金方式」の2つの方法があり、選び方によって手取り額が大きく変わることもあります。
老後の生活資金になる大切なお金なので、慎重な判断が必要です。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
●一時金で受け取る
・税金の計算:退職所得(退職所得控除)
・メリット:税負担が軽減できる可能性がある/社会保険料がかからない
・デメリット:資金を計画的に管理する必要がある
●年金で受け取る
・税金の計算:雑所得(公的年金等控除)
・メリット:資金管理がしやすく、計画的に使える
・デメリット:税金や社会保険料の負担が増える可能性がある
税務署に相談に行った背景

夫は勤務先の組織変更により50歳で転籍になり、退職金が支給されることになりました。ところが、実際に受け取る段階になってみると、受け取り方の選択肢が非常に多く簡単には決められないことがわかりました。
退職金のほかに、企業年金など複数の内訳あり、それぞれを「一時金」「年金方式」「一時金と年金の併用」を選択することができ、さらに受給開始年齢の調整もできたので、選択肢は15~20通りにもなったのです。
私の悩みが大きくなったのは、選択のタイミングが50歳前だったので、公的年金の見込額が不確かだったことです。さらに、iDeCoにも加入しており、今後も継続予定だったことで将来の税金への影響をどう考えるかが課題となりました。
iDeCoは受け取り方によって「退職所得」か「年金の雑所得」になるため、他の退職金との組み合わせで税負担が変わる可能性があるのです。
特に、一時金でまとめて受け取る場合は、受け取る時期や順番にも注意が必要でした。
いくつかのパターンでシミュレーションをしてみましたが、「これがベスト」と言い切れる答えが出せず、制度を正確に理解するために税務署に相談に行くことにしました。
税務署での相談と驚きの一言
税務署で相談内容を伝えると、最初に言われたのが、
「税務署では『お得なもらい方』はお教えできません。お得なもらい方はFPの分野です。」という言葉でした。
税務署には私がFPであることは伝えていませんでしたが、この言葉を聞いて、改めて「家計の個別の事情のご相談にのるのはFPの役割なんだ」と実感しました。
税務署では、「税金の計算方法」や「制度の仕組み」についての基本的な説明を受けられましたが、具体的なアドバイスや、私の用意したシミュレーションの確認まではしてもらえませんでした。
この経験から得たこと
税務署は「制度の枠組み」は教えてもらえるけれど、個別のケースに踏み込んだ相談をする場所ではないことを改めて感じました。
ただ、私にとってこの経験は、相談者の立場になることで、「不安な気持ち」「選択肢が多すぎて決められないもどかしさ」を感じ、答え見つからなかった場合の残念な気持ちを身をもって体験できました。
制度の仕組みを伝えるだけではなく、相談者の悩みに寄り添い、選択の整理を一緒に行うFPでありたいと改めて思う出来事でした。
家計相談をご希望のかたはこちらよりご連絡下さい。