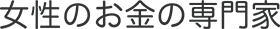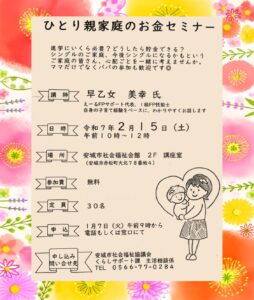知っておきたい!高校生のための就学援助(返還不要の給付金など)

皆さま、こんにちは。
マイライフエフピー®認定ライター・認定講師の
女性のお金の専門家 山﨑かづ偀です。
実は、我が家は受験シーズンの真っただ中です!
我が家の娘は今、中学3年生です。
入学検定料の振込で銀行に走ったり、返信用のレターパックを買いに郵便局へ走ったり、野菜多めのメニューを考えたり、私も受験生の親として何かと気ぜわしい日々を送っています!(笑)
受験生の皆さま、心配しているご家族の皆さま、
ごいっしょに厳しい冬をがんばって乗り越えましょうね!
さて、わが子の成長は嬉しいものですが、高校生ともなると、実際は色々とお金がかかりますよね。
そこで、高校生のお子さんをお持ちの方、これから高校進学を控えているお子さんをお持ちの方に、
ぜひ知っておいていただきたい、支援制度があります。
ご参考になりますと幸いです。
【国の就学支援制度とは?】

国の支援制度として、授業料に充てるための給付金があります。
(もちろん返還は不要です!)
正式名称は「高等学校等修学支援金制度」といいます。
所得要件を満たす世帯は、授業料の支援が受けられます。
それまでは、所得要件ごとに支援金額が異なっていましたが、上限金額が一律に引き上げられたのです。
以下にポイントを挙げてみます
●年収が約910万円未満の世帯は支援が受けられます。
●在籍する学校で申し込みます。新入学生は4月に学校で配布される資料を要チェックですね!
在校生(新2年生以上)は7月頃に学校から案内があります。
●所得要件を満たせば、国公私立を問わず、支援が受けられます。
※支援金額は公立と私立で異なります。
気になる支援額は?

●公立:年間11万8,800円(月額9,900円)
●私立(全日制):年間39万6,000円(月額33,000円)
●私立の通信制高校は年間29万7,000円(1単位当たり約12,000円)
※なお、通信制高校は卒業所要単位(72単位)を1年当たりで換算して(毎年24単位ずつ取得するとして)、
1単位当たりの金額を求めています。
〈所得要件について〉
この制度を利用するためには、所得要件を満たす必要があります。
少し難しいですが、以下の計算式で求められます。
保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額
→30万4,200円未満なら支援対象となります
※課税標準額は、住民税のお知らせ(毎年6~7月に届く細長い紙)に「課税標準額」として書かれています。
また、課税証明書では「課税総所得金額」として書かれています。
【ご参考】〈大阪府の高校無償化について〉

大阪府の高校無償化制度は、上記の所得要件を満たさない世帯もすべて対象とするためにスタートしました。
2024年度から段階的な支援がスタートしています。
※2025年春からは新高校2年生と3年生が授業料無償化になります!
今(2025年1月現在)の中学2年生からは全員が無償化の対象となります。
この制度が全国的に広まってほしいものです。
子育て世帯の負担がもっと少なくなり、安心して子育てができるようになるといいですよね。
〈高校生等奨学給付金〉
上記の支援金(国の制度)は授業料についての補助です。
けれども、実際のところ、高校生ともなると授業料以外にも色々な費用が必要となりますよね。
通う学校によっては通学費用も掛かるし、教材も「学校指定のタブレットがかなり高額だった!」
というような、ママさんのお声も聴きます。

そのような授業料以外の教育費に対する給付金があります。
正式名称は「高校生等奨学給付金」です。
こちらは、各都道府県が主体となっている制度です。
対象となる世帯は非課税世帯等です。
前述した、国の授業料支援(「高等学校等修学支援金制度」)と同様に、
通学している学校を通じて申し込みます。
気を付けていただきたいのですが、私立の学校によっては、この制度の対象とならない場合があります!
ちなみに、我が家の娘が進学を希望している通信制高校は対象外でした。
ぜひ、お申し込みの前にお子さんの進学希望先が対象かどうか、調べておいてくださいね!
{対象となる世帯と給付金額}
対象となるのは非課税世帯です。
国公立か私立かによっても金額が変わってきます。
●生活保護受給世帯 国公立:年間3万2,300円
私立:年間5万2,600円
●非課税世帯(全日制)第一子
国公立:年間12万2,100円
私立:年間14万2,600円
●非課税世帯(全日制)第二子以降
国公立:年間14万3,700円
私立:年間15万2,000円
※第二子以降、金額が増えるのは嬉しいですね。
●非課税世帯(通信制・専攻科)
国公立:年間5万500円
私立:年間5万2,100円
なお、この制度は家計急変によって非課税相当になった世帯も対象となります。
具体的な手続きはお住まいの各都道府県の担当窓口にお問い合わせくださいね。
ご参考になりましたら嬉しいです。

ご質問もお気軽にお寄せくださいね!